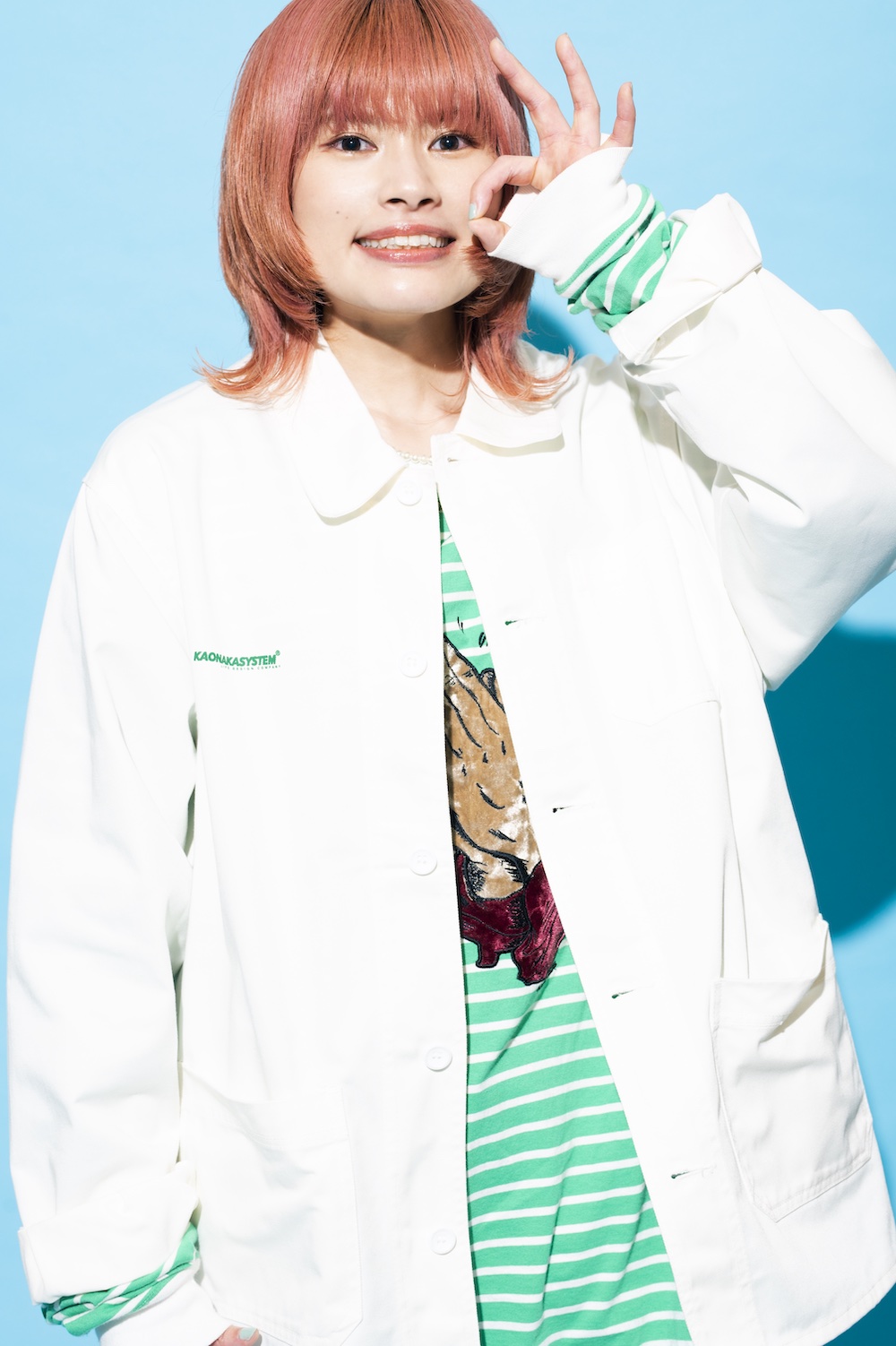アニメ『ラブオールプレー』のエンディングテーマとして書き下ろされた新曲「ライラ」に加え、4曲のライブ音源を収録したEP「ライラ」をリリースした男女ツインボーカルパンクバンド・LONGMAN。表題曲「ライラ」は、編曲に江口亮を迎え、綿密かつモダンなサウンドプロダクションが響く新機軸の一曲。そしてライブ音源は、LONGMANのパンクバンドとしての躍動を見事に刻んでいる。今年で結成10年目を迎えるLONGMANだが、その最先端と本質を捉えたこの新作EPについて、ツアー真っただ中の3人に語ってもらった。
INTERVIEW & TEXT BY 天野史彬
PHOTO BY 冨田望
■地元に支えられてきた。僕らの活動が恩返しになれば
──LONGMANは地元・愛媛を拠点に活動されていますが、地元の風土が自分たちの音や活動に反映されていると感じることはありますか?
ひらい:マイペースに活動できている部分ですかね。マイペースに“好き”を追求できている。
ほりほり:東京にいる僕らを見ると、めっちゃ田舎者感があると思います(笑)。
ひらい:いまだに東京タワーでテンション上がるもんな(笑)。
──(笑)。地元を拠点にしているのは、“マイペースさを保ちたい”という理由が大きいですか?
ひらい:絶対に愛媛に住み続けたいということでもないんですけど、単純に愛媛が好きやし、地元だから落ち着くっていう感じですね。今のところ東京に出てくる必要性もそこまでないですし。それに、地元の人たちに支えられながらゼロからずっとやってきたので、僕らの活動が恩返しになればいいなっていう気持ちもあって。
さわ:私たちが愛媛でライブをすることによって、地域の人たちにも何かプラスになるようなことがあればいいなって思うよね。
ひらい:思うよな。一応バンドマンですけど、“社会貢献したい”っていう気持ちも若干あるんですよ。
ほりほり:バンドマンは社会貢献しちゃダメなのか(笑)。
ひらい:いやいや(笑)。でも、例えば僕らのライブで愛媛に500人くらいの人が県外から集まったとするじゃないですか。そうしたら、移動費とか、飲食代とか、お金もそれだけ回るということで。それって嬉しいんですよ、愛媛県民としては。
さわ:私らがよく行くお店にファンの方が来てくれたっていう話を聞くとすごく嬉しい。地元で活動しているからこそあることだなって思う。
ひらい:最終的には、愛媛で僕たち主催のフェスとかができたら嬉しいなって思いますね。
■コロナ禍ならではのライブの楽しみ方を見つけられている
──現在LONGMANはツアー『TOUR 2022“This is Youth”』中ですが、そのファイナル公演も松山のライブハウス“WStudioRED”ですね。この取材はツアーも中盤に差しかかった頃に行っているんですけど、現時点でのツアーの手応えはいかがですか?
ほりほり:そもそも、コロナ禍の規制に対しての戸惑いもあったし、コロナ禍でライブの本数が減ったことで、バンドのライブ感に衰えを感じていた時期もあって。やっぱり、ライブってやり続けていないと感覚は鈍るものなんだと思います。でも、今年の2月にはインディーズ時代のアルバムの曲を会場ごとに分けて全曲演奏するコンセプトツアー(『BACK TO THE 20XX』)もできたし、ライブに対する向き合い方が戻ってきたなかでの今回のツアーなので。グルーヴ感というか、3人でひとつの音を出す感覚をまた掴みつつあるなっていう感じがしています。
ひらい:やっと、コロナ禍でのライブを純粋に楽しめるようになってきたなと思いますね。最初は僕ら自身もお客さんもやっても大丈夫なこととダメなことの線引きは難しかったと思うんですけど、最近やっと何がやっていいことで、何がやってはいけないことなのか、言葉にして言えるようになってきた感じなんですよね。「ここは手拍子!」とか言ってあげるとお客さんも動きやすくなるんだなっていうこととかもわかってきたし、ガイドラインのなかで一緒に楽しむやり方がわかってきた。お客さんに届いている手応えもすごく感じています。もちろん、寂しさはありますけどね。でも、今は今でやることをやっていかなきゃなって思いながらやっています。
さわ:私はよくTwitterでエゴサをするんですけど、それを見よったら、「LONGMANのことはほぼ知らんけど、友達に誘われてツアーに行ってきた」って呟いている人がいたんです。しかも、その人がめっちゃLONGMANにハマってくれたみたいで。コロナ禍以前のライブだったら、こうはなっていなかったかもなと思うんですよ。私たちのライブって、以前はモッシュもダイブもめっちゃ多くて。もしかしたら、ああいうグチャグチャなフロアだったら、初めましての人たちは一歩引いてしまったかもしれない。でも、ちゃんと自分のスペースが確保できる今の状況だからこそ新しいお客さんも入ってきやすくなっているのかなと。
──たしかに、ライブは慣れない人にとってはハードルが高いものだけど、今は入り込みやすいタイミングなのかもしれないですね。
さわ:あと、コロナ禍前までは、私たちのライブってフロアからのお客さんの声がすごかったんですよ。
ひらい:野次がすごかった(笑)。
さわ:野次の中で会話をしているような感じだったんですけど(笑)、今はそれができなくなったので、MC中にみんなにTwitterでハッシュタグを付けて呟いてもらって、それでお客さんと会話をするっていう初の試みをしていて。お客さんが言いたいこととか、私たちに訊きたいことを、私たちがその場で読むっていうコミュニケーションをしているんです。それがめちゃくちゃ楽しいんですよ。楽しすぎて、最初の頃はライブの時間が延びすぎてしまって、スタッフさんに怒られました(笑)。
一同:あはは(笑)。
さわ:でもTwitterを見るかぎり、この試みはお客さんにも喜んでもらえていたみたいで。コロナ禍ならではの楽しみ方はどんどん見つけられているのかなって思います。
──LONGMANって、新しい要素を取り入れていくことや、自分たちの表現を広げていくことに対して非常に柔軟だし貪欲な印象があるんです。それは今のライブの手法の話を聞いても思いますし、緻密に進化した新曲「ライラ」のサウンドを聴いても感じるところで。そうした活動の在り方は、自然と根づいていたものなのか、それとも意識的に手に入れていったものなのか、どう思いますか?
ひらい:そこは、わりと意識的だと思います。
ほりほり:基本的に不器用な3人なので、意識的に取り組もうとしないと、新しいことができないタイプなんですよ。降ってくるというよりは、スタッフさんと話し合いながら、頭の中で試行錯誤している感じだと思いますね。
ひらい:特に今って、何も考えていないとすぐに拗ねちゃいそうになるんですけど、そこをあがいていかないとバンドも終わっていくだろうなと思うし。自力のないバンドは生き残れない世界になっていると思うんです。ライブに足を運ぶお客さん自体も減っていっているような気もしますし、そのなかでどうやって生き残っていくのかは考えます。どのバンドも、今はほんまにもがいていると思いますけど。
──さわさんはどう思いますか?
さわ:新しいことを受け入れることに対して、私はもともと抵抗があまりなくて。ちょっとでも“楽しそう”と思ったら“それでOK”みたいな感じなんですよ。細かいところは周りのみんなが考えてくれるし(笑)、私はただ、その場を楽しむだけっていう感じでやっちゃってます。
ひらい:(さわは)楽しむ役やからな(笑)。
さわ:この間も、ライブ中すっごい楽しくて。それでステージ上を走り回っていたら、カメラマンさんがその姿を写真に撮っていたんですけど。その写真を見たときに、“LONGMANやってて良かった”と思いました(笑)。何の話やっていう感じだと思いますけど(笑)、“楽しい楽しい”とは思っていたけど、“私、こんなに楽しそうやったんや”と思ったんですよ。
ひらい:俺もあの写真見て、“この笑顔を守らなあかん”と思った。
一同:あはは(笑)。
ひらい:“このバンドで売れなあかんな”って(笑)。
■「ライラ」は、僕らにとっては変換点になる曲
──EP「ライラ」は、先ほども言ったように1曲目の「ライラ」が緻密に作り込まれた楽曲で、バンドの音楽性の進化を感じさせますが、他の4曲はライブ音源で、LONGMANの本質的で肉体的な面を色濃く感じさせますね。一作の中に非常に多面的な魅力が詰まった作品だと思います。まずライブ音源のほうから伺うと、自分たちで自分たちのライブの演奏を聴くのって、どういう気持ちになるものですか?
ひらい:もどかしいっすね(笑)。
さわ:こっぱずかしくなります(笑)。ライブ映像を確認することもよくあるんですけど、そのときは大丈夫なんです。でも音源となると、目で見るんじゃなくて、耳だけの情報になるじゃないですか。客観的に“ああ、自分ってこんな感じなんだ”と思って、こっぱずかしくなる。でも、今回のEPのライブ音源は本当に、いつものLONGMANのライブが捉えられていると思うし、LONGMANのライブに来たことがない人たちでも、空気感がわかってもらえると思います。「Will」、「1919」、「WALIKING」、「Hello Youth」っていう選曲も、“これを聴けばLONGMAN入門編になるよ”っていうものなので。楽しい一枚になりました。
──1曲目「ライラ」は、音楽的にはどのようなイメージがありましたか?
ひらい:2020年にマシン・ガン・ケリーが、ラッパーなんですけどポップパンクアルバム(『Tickets to My Downfall』)を出したんです。Billboardで1位を獲ったりするくらい話題になったんですけど、僕としてもそれがめちゃくちゃ衝撃だったんですよね。ポップパンクだけど、バックグラウンドにヒップホップがあるからすごく新鮮なアプローチがいっぱいあって。“これ、めっちゃ新しい!”と思ったんです。パンクって、それまではちょっと下火なイメージもあったんですけど、マシン・ガン・ケリーのアルバムはパンクロックの希望やと思って。「ライラ」はそこに影響を受けている部分は大きいと思います。トラップビートを取り入れてみたり、アレンジャーの江口(亮)さんが入れてくださったシンセがあったり。今までのポップパンクにはなかったアプローチを随所に入れられたという点でも、僕らにとっては変換点になる曲だと思いますね。
──それだけダイレクトに影響を受けるくらい、マシン・ガン・ケリーの存在は大きかったんですね。
ひらい:めちゃくちゃ大きかったです。めっちゃ聴きましたし、ほんまに希望やと思いました。“まだパンクで新しいことできるんや”って。
──ほりほりさんはセルフライナーノーツで、「大きな気持ちの変化をもたらしてくれた一曲」と書かれていましたね。
ほりほり:今回はひらいさんと江口さんが作ったリズムパターンをそのまま叩くっていう感じだったんですけど、僕、他の人が作ったドラムを叩く経験が今まであまりなかったんですよ。自分でドラムパターンを作ると、どうしたって自分が叩きやすいものになることが多いんですけど、今回は自分で作っていないがゆえに、無力さを感じることも多くて。ただ逆に言うと、自分のできないことが見えたぶん、“これとこれができるようになれば評価してもらえるんだろう”というのも見えてきたんです。僕は“ここで結果を出せば先に行ける立場なんだ”ということを、今さらですけど(苦笑)、知ることができた。
──でも、すごく大きな変化ですよね。
ほりほり:そうですね。僕個人としても分岐点の曲です、「ライラ」は。今まではあくまでも“LONGMANのドラマー”という意識でしたけど、純粋にひとりのドラマーとして評価されたいという意識が芽生えてきました。
ひらい:ドラムに限らず、全楽器に対して、自分らで作っていた限界を江口さんが突破してくれた感じはありましたね。挑戦することの大事さは僕も実感しました。ほりほりの意識の変化も、今後のLONGMANの曲作りにめっちゃ活きてくるんじゃないかと思うし。
──さわさんは、どのように「ライラ」に向き合いましたか?
さわ:歌詞の内容も反映されているのかもしれないですけど、今までの曲よりも強く、世界観にのめり込んで歌ったと思います。作詞は全部ひらいさんですけど、いつも以上に、自分に重なる部分が多かったんですよね。
──「ライラ」の歌詞は、“君”という存在が歌われているところに心を掴まれました。現実に近くにいるものであっても、あるいは遠く手の届かない場所にいるものであっても、ひとえに“君”という存在が生きることの支えとしてある、その感覚が歌われているように感じて。それはどこか、バンドのことを歌われているようにも受け取れますし。
ひらい:『ラブオールプレー』のエンディングテーマということで、物語の主人公に寄り添いつつ、部活でみんなと上を目指していくという原作を意識して書いたんですけど、バンドも似たようなものなので。自分の夢を他の人が一緒に見てくれるっていうのは本当にありがたいことだなと思うんですよね。自分のために頑張るのもいいですけど、人のために頑張ったほうが、頑張れることってあるんじゃないかとも思うので。
さわ:男女ツインボーカルだからこそ、その部分がより際立って感じられるんじゃないかと思います。ひとりで歌うより、ふたりで歌っているほうが“君”を感じられるんじゃないかって。私自身、誰かが一緒におってくれたり、誰かが応援してくれたり、背中を押してくれたり……そういうことが、バンドをやるうえでの活力になったりするので。
■パンクには、個人個人の中に日々、溜め込まれたものを発散する力がある
──LONGMANは今年で結成10年ということですが、感慨はありますか?
ひらい:あまり実感はないんですけど、とはいえ、バンドを結成したときの最初の目標が“一日でも長くバンドをやる”だったので、そういう意味では、10年経っても同じメンバーで続けることができているのは感慨深いです。
ほりほり:僕としては、スタッフの方々が僕らの可能性を信じ続けてくれたことへの感謝が、この10年間に対していちばん思うことかもしれないです。なんだかんだ、休止期間もあり、コロナ禍もあり、うまくいかないことも多い10年間だったけど、その間も僕らを支え続けてもらえたことが嬉しい。バンドを続けるのって大変なんですよね。人それぞれ生活があるなかで、同じメンバーでい続けることの難しさってすごく感じるので。
さわ:コロナ禍になってから、余計にそれは思うね。周りを見てると……。
ひらい:そうだね。解散したバンドもいっぱいいるからね。
ほりほり:なるべく、今のメンバーで続けたいです。
──ひらいさんは先ほどマシン・ガン・ケリーのことを“パンクロックの希望”とおっしゃいましたけど、皆さんはなぜ、パンクに惹かれるのだと思いますか?
ひらい:なんでパンクが好きか……? あんまり考えたことなかったです。広瀬すずが好きっていうくらい本能的なことやったわ。
一同:あはは(笑)。
さわ:好きになった人が好き、みたいなことでしょ?
ひらい:そうそう。
ほりほり:そういう直感的なものだよね。僕も“いいメロディだな”“いい歌詞だな”“カッコいいドラムの音だな”っていう直感で音楽を好きになってきたし。特にパンクの良さって、シンプルさにあると思うんですよ。僕がカッコいいと思う音楽って、結局はグッドメロディとグッドリフなんです。それにプラス、今だったら打ち込みとかもありますけど、原点はやっぱりグッドメロディとグッドリフ。すごく単純でわかりやすい部分だと思う。自分らの武器は何かっていうことを最近よく考えるんですけど、僕はやっぱり、ひらいさんの書くグッドメロディが僕らの武器だと思っている。
──すごく本質的な部分ですよね。そこがブレないから、LONGMANは広く発展していけるし、実験していけるんだと、「ライラ」を聴いても感じます。
ひらい:僕は、10-FEETを見て、SUM 41を見て、ハイスタ(Hi-STANDARD)を見て、“自分もこうなりたい”と思ったからこそバンドを始めて。ただ、彼らと同じことをやるんじゃなくて、自分の中でもっと音楽でワクワクできるように新しいものを探していきたいという気持ちのもとに、今頑張ってる。それが楽しいです。まだ自分が理想とするカッコよさに近づけてはいないけど、追い求めていること自体が楽しいし、これを続けていきたい。一日でも長くバンドをできるように頑張っていきたいです。
──なぜ、パンクを選んだのか。さわさんはどう思いますか?
さわ:私は“バンドが好きだ”って自覚を持ったのはELLEGARDENが最初だけど、そこからSpecialThanksのミュージックビデオを観て、“同年代くらいの女の子がこんなにカッコいい音楽をやっているんだ!”って衝撃を受けて。それまでは、バンドって男性がやっているイメージだったんですよ。“男の人の世界だ”って勝手に思っていて。でも、そうじゃなかったっていう衝撃。そうやって受けた衝撃って、今も色褪せることなくずっと自分の中に残っているんですよね。
──なるほど。
さわ:あとは、ある意味、ストレス発散みたいなものなのかもしれない。生きているのって楽しいことばっかりじゃないし、むしろ、そうじゃないことのほうが多かったりするけど、それを凝縮して外に発散できる。反発とかっていうよりは、そういう個人個人の中に日々、溜め込まれたものを発散すること。私にとっては、そういう力がパンクにはあるのかもしれないなって思います。
ほりほり:今は特に大変やからね。コロナ禍で締め付けられてきたものもあるし。もしかしたら今は、パンクバンドにとって転機なのかもしれないですね。
リリース情報
2022.05.04 ON SALE
EP「ライラ」
プロフィール
LONGMAN
ロングマン/さわ(Vo, Ba)、ひらい(Gt, Vo)、ほりほり(Dr, Cho)、3名による四国・愛媛発の男女ツインボーカルパンクバンド。2012年より現在のメンバーで活動をスタートし、2019年6月にインディーズ集大成となるベストアルバム『Dictionary-indies BEST 2013-2019』をリリース。同年11月にTVアニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』エンディングテーマのタイトル曲を含むシングル「Wish on」でメジャーデビュー。
LONGMAN OFFICIAL SITE
https://longman.jp/